ヒョウモントカゲモドキの繁殖方法について!クーリングなど必要な準備を紹介!!
ヒョウモントカゲモドキは簡単に繁殖させることができます。ヒョウモントカゲモドキを初めて飼育した人でも、少し飼育に慣れてしまえば簡単にヒョウモントカゲモドキを繁殖させることができます。今回の記事ではヒョウモントカゲモドキを繁殖させるために必要な準備を方法を紹介します。
ヒョウモントカゲモドキに限らず、生き物を飼育していると繁殖に挑戦してみたくなりますよね。
ヒョウモントカゲモドキを飼い始めてばかりの人でもちゃんと飼育することができれば、簡単に繁殖させることができます。ただ、繁殖や産卵は体力を使うので、繁殖させる場合はしっかりと準備をする必要があります。
今回の記事ではヒョウモントカゲモドキを繁殖させるために必要な準備を紹介するので、ヒョウモントカゲモドキの繁殖に挑戦してみたい人はぜひ読んでみてください。
それでヒョウモントカゲモドキを繁殖させるために必要な準備を紹介します。ヒョウモントカゲモドキの繁殖方法についてはこちらの記事で詳しく紹介しているのでそちらも読んでみてください。
レオパの繁殖について!!ヒョウモントカゲモドキの繁殖方法と手順、注意点を紹介!!
繁殖する前の注意点
まずは繁殖に挑戦する前に繁殖させる際の注意点を紹介します。
繁殖には負担がかかる
繁殖行為は体力を使うので、親個体に負担がかかります。特にメスは卵を作るために栄養を使うので、体力を消耗します。
体力のない個体だと抱卵する際に体調を崩してしまうことがあるので注意してください。繁殖は体力を消耗させるので、親個体の体調を優先して体調がすぐれない場合は繁殖を見送るようにしましょう。
生まれた子供をちゃんと飼育できるか
ヒョウモントカゲモドキは1度の交尾で最大で10個の卵を生みます。
もし10匹のレオパが生まれた場合自宅で飼育できるのかよく考えてから繁殖に挑戦しましょう。ペットショップによっては生まれたレオパを引き取ってくれるお店もあります。また、里親になってくれる方もいるので、繁殖に挑戦する場合は生まれた子供の行き先を確保しておきましょう。
ヒョウモントカゲモドキを繁殖させる準備について
レオパを繁殖させるための準備について紹介します。繁殖は体力を消耗するので、しっかりと準備をして安全に繁殖させるようにしましょう。
それでは繁殖させる準備について紹介します。
繁殖可能なサイズまで成長させる
セミアダルトを飼育している場合は繁殖が可能なサイズまで成長させましょう。
ヒョウモントカゲモドキが繁殖可能なサイズはオスで50gメスで45gといわれています。
このぐらいのサイズになるまでは繁殖はできないので、ちゃんと繁殖可能なサイズに成長するまでは待ってください。
メスが未熟な場合、最悪オスと喧嘩をしてどちらかが怪我をしてしまうことがあります。また、もしも産卵に成功しても、無精卵だったりしてちゃんとヒョウモントカゲモドキの赤ちゃんが生まれないことがあります。
だいたい1年ぐらい飼育していれば、そのぐらいのサイズまで成長するので、ヒョウモントカゲモドキを繁殖させる場合は、まずが1年間しっかり健康的に育てるようにしましょう。
餌とたっぷり与えて脂肪を蓄えさせる
ヒョウモントカゲモドキはしっぱに脂肪を蓄えて、餌の少ない冬の時期は尻尾の脂肪を燃焼させて活動します。
ヒョウモントカゲモドキを繁殖させるためには、クーリングといって、発情を誘発すつために大切なステップが必要になります。
クーリング中は1〜2ヶ月ほど餌を抜く必要があります。なので、ちゃんと餌を与えられず脂肪が蓄えられてない状態でクーリングを行ってしまうと個体にダメージを与えてしまい最悪死んでしまうことがあります。
尻尾がちゃんと太くなって、しっかり脂肪を蓄えられるようになるまではクーリングは行わずにしっかり飼育するようにしましょう。
痩せていたり、ちゃんと栄養が蓄えられていないと、卵から孵ったベビーもちゃんと成長できなかったり、親のヒョウモントカゲモドキも病気になったりして死んでしまうことがあります。
産卵、繁殖にはすごく体力を使うので、ヒョウモントカゲモドキの健康状態が良くない場合には繁殖を見送るようにしましょう。
体調が整ったらクーリングの準備をしよう
ヒョウモントカゲモドキは冬を越して春になってから繁殖をする習慣があります。なので繁殖に挑戦する場合はクーリングをする必要があります。クーリングをしないでも交尾をすることがあるので、まずはクーリングをしないで、ペアで飼育してみるのがいいと思います。
ペアで飼育しても交尾をしない場合はクーリングをするようにしましょう。
日本の気候上ヒョウモントカゲモドキのクーリングが行えるのは冬場になります。エアコンなどを使って室温を管理すればできないこともないですが、1ヶ月室温を20度以下にするためには電気代もたくさんかかってしまうので、クーリングは基本冬場になります。
クーリングが行える季節までに、ちゃんと餌を与えて脂肪を蓄えさせる必要があるので、ヒョウモントカゲモドキを繁殖さるには計画を立てておきましょう。
クーリングの季節までにヒョウモントカゲモドキの体調が整わない場合には、クーリングは見送ってヒョウモントカゲモドキの飼育に専念するようにしましょう。
クーリングのやり方
クーリングをしなくても交尾をすることがありますが、一緒に飼育しても交尾をしない場合は、繁殖のスイッチを入れるためにクーリングを行うようにしましょう。簡単にクーリングのやり方について紹介します。
徐々に飼育温度を下げる
クーリングをする場合は1週間ほど餌を与えるのをやめます。1週間ぐらい餌を抜いて最後に食べた餌が消化さえてフンをしたことを確認したら、室温を1日に1度ずつぐらい下げて行って、最終的に18度ぐらいになるようにしてください。急激に温度が下がると体調を崩してしまうので気をつけてください。
18度前後で1ヶ月ほど飼育する
室温を18度前後にしたら、そのままの状態で1ヶ月飼育してください。この時も餌を与えずに水だけを与えて飼育します。ヒョウモントカゲモドキは尻尾に脂肪を蓄えているので、クーリングの前にしっかりと餌を与えて、脂肪を蓄えさせておけば、1ヶ月程度であれば餌を食べなくても問題ありません。
1〜2週間かけて徐々に温度を戻す
1ヶ月ほど低温で飼育したらまた、1日に1度前後温度をあげながら徐々に飼育温度をあげて行って、元の温度まであげてください。
温度を上げる際も急に上げると体調を崩してしまうので、1〜2週間ほど時間をかけて徐々に飼育温度を上げるようにしてください。
ヒョウモントカゲモドキの交尾について
クーリングをしたらあとはペアで飼育することで交尾を始めます。一緒の飼育ケージで飼育すると早ければ数時間で交尾を始めます。すぐにオスがメスに反応しなくても2〜3日ぐらいは用意を見るようにしましょう。だいたい2〜3日もすれば交尾が始まります。
オスは尻尾を震わせてメスにアプローチします。威嚇のようにも見えますが、喧嘩をすることは少ないのでそれほど心配することはありません。メスは尻尾を持ち上げてオスを受け入れます。
ヒョウモントカゲモドキはハーレムを作って繁殖をするので、オス1匹に対してメスを2〜3匹程度を一緒に飼育したほうが交尾をする確率が高いです。モルフなどのパターンを気にしない場合はハーレムで繁殖に挑戦してみるのがいいと思います。
ペアリングについて
オスとメスを同居させることをペアリングと言います。
ヒョウモントカゲモドキは大体初顔合わせで交尾をすることが多いです。相性がよければすぐに交尾を始めます。交尾は数分で終わるので交尾が終わったらオスとメスは別のケージに写してください。
すぐに交尾が始まらなくても2〜3日ほど一緒に飼育していると高確率で交尾をしてくれます。相性が悪いと喧嘩になることがあります。何度も繁殖に挑戦しても喧嘩をしてしまう場合は相性が悪いので他の組み合わせて繁殖に挑戦するのがおすすめです。
交尾後の飼育について
交尾が終わってもオスは繁殖期間が続きます。なので、同じケージで飼育しているとメスに負担がかかってしまうので、交尾が終わったらオスとメスは別々のケージで飼育するようにしましょう。
交尾が終わると餌をよく食べるようになります。卵や子供を作るためにも高い栄養価が必要なので、カルシウム材を添加してしっかりと餌を与えるようにしましょう。
抱卵について
交尾が終わって10日もするとメスのお腹に卵を見つけることができます。卵を持っている状態を抱卵と言います。ヒョウモントカゲモドキは1回に2個の卵を生むので、お腹の左右に一つずつ卵を持っています。
抱卵の期間は個体によって違いますが早いものでは2週間ほどで産卵します。遅いものだと2ヶ月ぐらい抱卵したままのこともあります。たまに卵がお腹の中で詰まってしまうこともあります。何ヶ月も産卵をしないようであれば獣医さんに見てもらうようにしましょう。
抱卵中は卵を作るのに栄養を使うので、メスが栄養失調になってしまうことがあります。抱卵中は栄養不足にならないようにしっかりと餌を与えてください。
抱卵中はメスの食欲が旺盛になるので、食べるようであれば毎日餌を与えるようにしてください。
産卵床を準備しよう
抱卵を確認できたら産卵床を準備しましょう。産卵床はヒョウモントカゲモドキの体がすっぽりと入るぐらいの大きさのタッパーなどに、バーミキュライトやヤシガラ土、ミズゴケなど保湿性の高い床材を敷いてください。
床材は握っても水がにじまない程度に湿らせておきましょう。
産卵床を気に入ってくれればヒョウモントカゲモドキは産卵床に穴を掘ってそこに産卵します。
ただ、産卵床が気に入らないとその辺に産卵してしまうことがあります。その辺に産卵してしまっても乾燥する前に産卵床に戻してあげれば問題なく孵化させることができます。
また、水入れに産卵してしまうこともあります。水入れに産卵してしまうと卵は呼吸することができないので、そのまま死んでしまうことが多いです。産卵が近くなってきたら水入れはケージから取り出して、毎日霧吹きをして水が飲めるようにしておきましょう。
産卵が近くなるとメスは餌を食べなくなります。お腹が大きくなって餌を食べないようであれば産卵が近いので、それまでにはちゃんと産卵床を用意しましょう。
ヒョウモントカゲモドキの産卵について!産卵床や産卵前の行動、産卵した時の対処法を紹介!!
ヒョウモントカゲモドキの孵化について
卵は上下が変わらないように管理してください。
ヒョウモントカゲモドキの卵は一度胚ができてから卵の向きが変わると孵化しなくなってしまいます。なので、そのままケージ内に卵を入れているとメスが卵を転がしてしまい孵化しないことが多いです。
産卵床に卵を見つけたら、卵の上下が変わらないようにマジックで印をつけてなるべく早く取り出してください。産卵してから1日ほどで胚の向きが決まってしまうので、1日以内に取り出してください。
その後25〜30度前後の環境で、湿度が下がらないように80〜90%ぐらいの湿度を保つことで孵化させることができます。
タッパーなどに卵を写したら湿度が下がらないようにラップをかけてください。ラップをかけたら通気性を確保するために爪楊枝でいくつか穴を開けてください。
温度によって孵化までの期間は変わりますが1〜2ヶ月程度で孵化します。
ベビーの飼育について
生まれたすぐの子供はまだ栄養が残っています。
なのですぐに餌を与えても食べてくれません。最初に餌を与えるのは脱皮を終えてから1〜3日ほどしたら与えてください。
ベビーは温度の変化で体調を崩してしまうことが多いので、温度管理は徹底して急に温度が下がったりしないようにしましょう。
ベビーは体を作るためにたくさんの栄養が必要なので餌は毎日与えてください。
爬虫類の飼育に必要な設備についてはこちらの記事で紹介しているので、爬虫類の飼育を考えている方は読んでみてください。














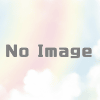



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません