レオパの繁殖について!!ヒョウモントカゲモドキの繁殖方法と手順、注意点を紹介!!
ヒョウモントカゲモドキを繁殖させるための準備が整ったら、早速繁殖に挑戦してみましょう。前回の記事ではヒョウモントカゲモドキを繁殖させるために必要な準備を紹介しました。今回の記事ではヒョウモントカゲモドキを繁殖させる方法と紹介します。
ヒョウモントカゲモドキはしっかり飼育ができていて、健康管理がちゃんとできていれば誰でも簡単に繁殖させることができます。ヒョウモントカゲモドキを飼育し始めて、飼育に慣れてきた人はぜひ繁殖にも挑戦してみてください。
爬虫類の中では繁殖が簡単な種類なので、繁殖に関する情報も多いので、ヒョウモントカゲモドキの飼育に慣れて入れば簡単に繁殖させることができます。
繁殖可能なオスとメスを用意する
まず、ヒョウモントカゲモドキを繁殖させようと思ったら、繁殖可能なオオスとメスを用意しましょう。
ヒョウモントカゲモドキは飼育1年以上の個体であれば繁殖が可能になります。
オスはメスよりも成長が早いので1年未満でも繁殖させることもできますが、メスはしっかり成熟していないとちゃんと卵を産まないので、生まれていか1年以上経っていて、体重が45g以上ある個体を用意しましょう。
ヒョウモントカゲモドキのメスが未熟だと、せっかく卵が産まれても無精卵だったり、卵を産んでも1個だけで終わりってことがあります。
また、未熟なメスはオスを受け入れずオスに対して攻撃してしまいます。メスがオスに攻撃しているようだったら、そのペアでの繁殖は諦めて別のケースに移してください。
オスとメスの見分け方
オスとメスを見分けるためには、尻尾の付け根を確認してください。
ヒョウモントカゲモドキのオスは尻尾の付け根に丸い玉が2ついていて、その少し上に鱗がたくさんついています。それに比べてメスは尻尾の付け根から後ろ足の付け根にかけて膨らみや鱗がなくつるっとしています。
見てみれば簡単にわかると思いますが、わからない場合は購入する際に店員さんに聞いてオスとメスを選んでもらうのがいいと思います。
性成熟していないと尻尾の付け根の膨らみが小さく見分けるのが難しいので、ベビーを購入するときは気をつけてください。
ヒョウモントカゲモドキのオスメスの見分けかたはこちらの記事で紹介しているので、こちらも読んでみてください。
ヒョウモントカゲモドキの雌雄判断する方法を紹介
ペアで繁殖させるかハーレムで繁殖させる
野生のヒョウモントカゲモドキはオス1匹に対して複数のメスで群れを作ってハーレム状態を作って繁殖をします。
なので、ヒョウモントカゲモドキを繁殖させようと思ったら、オス1匹に対して3匹前後のメスを用意してハーレム状態を作ったほうが簡単に繁殖させることができます。
ただ、ヒョウモントカゲモドキはカラーや模様のパターンを親から受け継ぎやすい種類なので、計画的にカラーや模様のパターを出したい場合は1対1のペアで繁殖させる方がいいと思います。
複数のメスを用意してハーレムを作ってしまうと、どのペアとの卵かわからなくなってしまいますので、計画的にカラーや模様のパターンを出すことができなくなってしまうので注意してください。
単純に繁殖させてみたいって場合はハーレムを作って繁殖させた方がいいと思います。ハーレム状態だと、どのペアの卵がわからないので、どんな模様が出るかわかりませんが、初めて繁殖に挑戦する場合はそっちの方が楽しいと思います。
クーリングをする
クーリングをしなくてもペアで飼育しているだけで繁殖することがあります。ペアで飼育しているだけで繁殖行動をするならクーリングをする必要はありません。もし、ペアで飼育していても繁殖行動をしないようであればクールングをしてください。
クーリングは低温処理とも呼ばれていて、ヒョウモントカゲモドキを冬眠させることで、春になったときに発情させて繁殖を促すことができます。
クーリングを行う場合は、最初に1週間餌を抜いて最後に与えて餌が糞となってでてきたことを確認してからクーリングを行ってください。
お腹に餌が残っている状態で冬眠してしまうと、お腹の餌が腐ってしまって冬眠中に死んでしまうことがあるので、ちゃんと最後にあげた餌が消化されたことを確認してからクーリングを行ってください。
クーリングの方法は30度前後で飼育している室温を2週間かけて徐々に下げていき、18度まで下げてください。1週間で5度ずつ下げて行ってください。
厳密に18度まで下げる必要はありませんが、だいたい18度ぐらいまで下げるようにしてください。18度前後まで室温を下げたら、1ヶ月ぐらいそのままにしてください。
クーリング中は餌を与えないで水だけを与えましょう。1ヶ月間餌を与えないと餓死してしまうんじゃないかって心配になるかもしれませんが、ヒョウモントカゲモドキには太い尻尾があってそこに脂肪を蓄えているので、1ヶ月ぐらい餌を与えなくても平気です。
餌を与えないことと、室温の低下でヒョウモントカゲモドキは冬が来たと思います。1ヶ月ほど餌を与えず、18度前後の室温で飼育したら、次は少しずつ室温をあげていきましょう。
熟成しているメスはクーリングを行わなくても、ちゃんと繁殖することができますが、クーリングを行った方が孵化率が高くなるようなので、面倒でもメスもクーリングを行っておいた方がいいと思います。ヒョウモントカゲモドキの繁殖方法、クーリングなど必要な準備を紹介!!
抱卵
後尾後メスは少しずつお腹が大きくなって、卵が透けて見えるようになります。交尾が終わった後からメスは抱卵のために餌をたくさん食べるようになるので、栄養価の高い餌をしっかりと与えてあげてください。
卵を産むまでの期間は個体によって差がありますが、早いものでは半月ぐらいで産卵をします。長いものでも2ヶ月ぐらいで産卵をするので、2ヶ月をすぎても産卵をしない場合は獣医さんに見てもらうようにしましょう。
産卵の準備について
メスのお腹が大きくなると産卵が近いです。産卵させるためには産卵床を用意する必要があります。
産卵床はヒョウモントカゲモドキの体がすっぽり入ることができるぐらいの大きさのタッパーに、バーミキュライトやミズゴケを入れて使用してください。
ミズゴケやバーミキュライトを5cm程度敷いて、乾燥しないように霧吹きをして産卵床を湿らせて置いてください。
また、個体によっては水入れの中に産卵してしまうことがあります。水入れの中に産卵してしまうと、卵が呼吸できずに死んでしまうので、産卵が近ずいてきたら飼育ケージ内から水入れを取り出しておくのがいいと思います。
水入れを取り除いたら、ちゃんと霧吹きをして水が飲めるようにしておきましょう。ヒョウモントカゲモドキの産卵について!産卵床や産卵前の行動、産卵した時の対処法を紹介!!
卵の管理について
ヒョウモントカゲモドキは産卵床を掘って、そこに産卵します。通常ヒョウモントカゲモドキは1回に2つの卵を産卵します。
そのままにしていると孵化することはないので、ヒョウモントカゲモドキの産卵を確認することができたら、卵を取り出してください。ヒョウモントカゲモドキの卵は時間がたつと胚の位置が固定されてしまい、卵の向きが変わると孵化しなくなってしまいます。
なので、卵の向きがわかるように取り出す前に卵に印をつけて、上下がわかるようにしておきましょう。
卵を取り出したら、小さめのタッパーにミズゴケやバーミキュライトなどを入れて、湿らせてから卵を並べてください。
卵をカップなどに並べたら温度が30度前後で、湿度が80%前後の環境で維持することで、卵を孵化させることができます。
温度の変化が激しいと卵が死んでしまうことがあるので気をつけてください。爬虫類用の孵化器も販売されているのでそういったものを使用するのがいいと思います。
温度と湿度を管理することができればいいので、孵化器を使わなくても発泡スチロールと保温器具を使って温度と湿度を管理できれば、ヒョウモントカゲモドキを孵化させることができます。
ヒョウモントカゲモドキは無精卵を産むことがあります。無精卵は有精卵に比べて少し小さいですが、小さいからと言って全て無精卵という訳ではありません。ライトに透かして見ると無精卵には影が映らないので見分けることができますが、最初は無精卵、有精卵どちらの育てるようにするのがいいと思います。
無精卵は育てているうちにカビが生えてきたり、色が変色してしまったりします。カビだけであれば卵が死んでいるわけではないので、拭き取ってそのまま飼育することができます。
ただ、変色したり卵が凹んだりしている場合は孵化器から取り出すようにしてください。有精卵でもちゃんと育たないと変色してしまったり卵が凹んだりするので、そういった場合も取り出してください。ヒョウモントカゲの卵の管理方法を紹介
ヒョウモントカゲモドキは温度によって性別を固定することができる
ヒョウモントカゲモドキは管理する温度によって、オスかメスかをコントロールすることができます。
30〜31度前後で管理しているとオスとメスは半分ずつぐらい生まれます。28度以下、34度以上で管理しているとほとんどメスになります。32度前後で管理すると生まれてくる個体はほとんどオスなので、オスにしたい場合は32度前後で管理するようにしましょう。
特にこだわりがない場合は30度前後で飼育するのがいいと思います。
卵の孵化について
ヒョウモントカゲモドキの卵は1〜2ヶ月ぐらいで孵化します。ヒョウモントカゲモドキの孵化は温度に影響されていると言われてます。
温度の高い方が孵化するのが早いと言われてます。実際に温度によって季節を感じて、寒い時期に孵化しないようにしたり、気温が高くなったら早めに孵化をするのは合理的だと思います。
孵化が近づくと卵に水滴がついたり、薄く切れ目が入ります。孵化する時は心配になる気持ちもわかりますが、触ったりしないで見守るようにしてください。
幼体の飼育について
卵が孵化したらヒョウモントカゲモドキの幼体の飼育です。ヒョウモントカゲモドキの幼体は乾燥に弱いので、湿度が下がらないように気をつけてください。
幼体は孵化器の中で1日飼育して、翌日に飼育容器に移してください。ヒョウモントカゲモドキが乾燥しないように飼育容器にはミズゴケなどを敷いたタッパーを入れて、中のミズゴケを湿らせておきましょう。
ヒョウモントカゲモドキの幼体は孵化してから数日すると脱皮をします。脱皮をして脱皮した皮を食べてから餌を食べるようになります。なので、脱皮をしたら餌を与えるようにしてください。
幼体を飼育する時は室温を高めにして、しっかりを餌を与えて飼育するようにしてください。温度が高い環境の方が成長が早くなります。餌は幼体の間は食べるだけ与えて構いません。しっかりと成長するように幼体の時は食べるだけ餌を与えるようにしましょう。
餌は幼体の頭の半分か3分の1ぐらいのサイズを選びましょう。コオロギを与える時は後ろ足を切ってあげると食べやすくなります。
ヒョウモントカゲモドキの飼育方法や特徴、飼育に必要な設備を紹介!!
ヒョウモントカゲモドキの幼体を飼育するときに気をつけたい3つのこと!!
レオパの寿命はどのぐらい?ヒョウモントカゲモドキの平均寿命と長生きさせる方法を紹介!!
爬虫類の飼育に必要な設備についてはこちらの記事で紹介しているので、爬虫類の飼育を考えている方は読んでみてください。










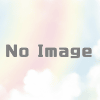



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません