カナヘビの餌について!カナヘビにオススメの餌と餌の与え方を紹介!!

カナヘビは日本に生息しているトカゲです。子供の頃に捕まえたことがある人の多いのではないでしょうか?見た目も可愛いのでペットとして飼ってみたい人も多いと思います。ただ、どんな餌を食べるのかわからないことも多いですよね。今回の記事では、カナヘビを飼育するときにオススメの餌を紹介します。
カナヘビは日本に生息しているので、草むらなどを探せば捕まえることができます。捕まえるのが大変だと思う場合はペットショップで販売もされていることもあるので、購入するのもいいと思います。
カナヘビは日本に生息しているだけあって飼育は簡単です。飼育環境をちゃんと整えて、餌をちゃんとあげていれば病気になったり死んでしまったりすることは少ないです。
今回の記事では、カナヘビの飼育にオススメの餌を紹介するので、カナヘビを飼育してみたいと思う人はぜひ読んでみてください。
それではカナヘビの飼育にオススメの餌を紹介します。
カナヘビについて
カナヘビと一言に言っても、実は種類が多く国内だけでも何種類ものカナヘビがいます。日本にはニホンカナヘビの他に、コモチカナヘビ、ミヤコカナヘビ、アムールカナヘビ、アオカナヘビ、サキシマカナヘビなどが生息しています。
ニホンカナヘビであれば捕まえて飼育することができますが、種類によっては捕獲や飼育が禁止されているので注意してください。
ニホンカナヘビは日本に生息しているカナヘビで、日本全国で見かけることができます。
春から夏にかけて見かけることが多く、午前中に石やブロック塀などで日光浴をしている姿を見かけることが多いです。トカゲは日光浴をすることで体温をあげて、代謝をあげます。
体温が下がっているときは動きが遅いので、午前中の日光浴をしている時のほうが捕まえやすいです。
カナヘビの餌は何がいい?
カナヘビは肉食なので昆虫を食べます。野生のカナヘビはクモやコオロギなどの小型の爬虫類を食べています。
飼育環境に慣れてピンセットから餌を食べるように慣れば、人工フードで飼育することができます。ただ、野生のカナヘビは人に慣れづらいので、ピンセットの給餌に慣れるまで、生きた昆虫を飼育ケースに入れて給餌するようにしましょう。
餌のサイズは、頭と同サイズぐらいであれば食べてしまいますが、吐き戻したりすることもあります。飼育する場合は頭より少し小さいサイズの昆虫を与えるようにしましょう。自然にいるクモやバッタなどを捕獲して与えることもできますが、1年を通して餌用の昆虫を採集するのは難しいと思うので、ペットショップで販売している餌用の昆虫を使うのがいいと思います。
餌は昆虫を与えるのが一般的ですが、昆虫だけだと栄養バランスが悪いので、カナヘビを飼育する場合は3匹に1匹程度の割合でカルシウム剤を餌にまぶしてから与えるようにしてください。
カナヘビの飼育にオススメの餌
ペットショップで購入することができる餌用の昆虫を紹介します。
コオロギ
カナヘビの餌として1番オススメなのはコオロギです。
ペットショップで販売もされていることもあり、手に入りやすいので簡単に購入することができます。どこのペットショップでもコオロギが売っているわけではありませんが、他の生き餌に比べて販売しているお店が多いです。
コオロギを購入しようと思ったら、コオロギが販売されているお店を探すか通販で購入するようにしましょう。通販の方が色々なサイズのコオロギが売っているので、飼っているカナヘビになったサイズのコオロギを購入できるのでオススメです。
カナヘビに限らずトカゲは自分の頭よりも大きい餌は食べられません。飼育しているカナヘビの頭の半分ぐらいのサイズのコオロギを購入する様にしましょう。
コオロギを保管する場合はちゃんとコオロギに餌をあげてコオロギの栄養価を高めておく必要があります。餌は果物の皮や野菜のくずなどを与えてください。
餌を用意するのが面倒な場合は昆虫用のゼリーでも構いません。ちゃんとコオロギに餌を与えておけば、コオロギの栄養価が高くなってコオロギを食べるカナヘビのためになるのでちゃんと餌を与えるようにしましょう。
コオロギの飼育方法はこちらの記事で詳しく紹介しているので、そちらも確認してください。コオロギを飼育しよう!爬虫類の餌に最適なコオロギの飼育方法を紹介!!
ミルワーム
ミルワームもカナヘビの餌にオススメです。
カナヘビが小さすぎるとミルワームを食べることができませんが、鳥や小動物の餌にも使われるのでペットショップで販売されていて、用意するのが簡単でオススメです。
脂肪分が多く栄養があまり良くないので、毎回あげていると脂肪過多になってしまうことがありあげすぎには注意が必要です。
鳥の餌用のミルワームがペットショップでよく売っているので、用意するのは簡単ですがあげすぎには注意が必要なので、コオロギなどの他の餌をメインにして、ミルワームはおやつとして与えるのがいいと思います。
ミルワームは蒸れに弱いので、夏場など湿度の高い時期はなるべく風通しが良くて涼しい場所で保管するようにしましょう。
直射日光が当たって温度が上がるとミルワームは死んでしまって黒くなります。死んだミルワームは匂いもキツイので保管する場合は気をつけてください。
温度が高いと成長が早くなってしまうので、なるべく大きくしたくないと思う場合は冷蔵庫で保管するのがオススメです。
ミルワームの場合もコオロギと同じで定期的に餌を与えましょう。ミルワームはなんでも食べるので、野菜のくずなど料理をした時に余ったものを与えるのがいいと思います。
ミルワームの飼育方法はこちらの記事で紹介しているので、こちらも確認してみて下さい。
養殖ブドウムシ
ブドウムシは釣りの餌として販売されています。
ブドウムシも脂肪分が多いので、与えすぎると脂肪過多になってしまいますが、栄養価が高いので弱っているカナヘビや餌をあまり食べない個体にはオススメです。
カナヘビのベビーに与えるにはサイズが大きいので、ベビーに与える場合は少し切って与えるようにしてください。
養殖のブドウムシはハニーワームとい名前でも販売されています。販売されている餌の中では1番栄養価が高いので、産卵した後のメスに与えたりするのにはオススメです。
サシ
サシは渓流釣りやカワハギ釣りなどで使われる釣り餌です。ブドウ虫よりもサイズが小さいので、体長の小さなカナヘビにオススメです。
ハエの幼虫で、ウジ虫がサシやサシ虫などという名前で販売されています。栄養価が高く、ミルワームの様に皮が厚くなく、ミルワームに比べて消化がいいので餌として使われることが多いです。
釣具屋さんで販売されているので購入しやすく、冷蔵庫で1週間ほど保存することができるので使いやすい餌です。サシには紅サシと言って、赤く着色されているものが販売されています。着色剤はカナヘビに悪影響があるかもしれないので、着色されていないサシを購入する様にしましょう。
他の生き餌の様に返しのある餌皿に入れておけば逃げないので与えやすくてオススメです。
デュビア
デュビアはいわゆるゴキブリです。日本に生息しているゴキブリとは見た目が違うのでそれほど気持ち悪くはありません。コオロギのように鳴かないのでうるさくなく、飼育も簡単なのでカナヘビの飼育にもオススメの餌です。
他の生き餌に比べて匂いも少ないので、飼育はしやすい餌です。ただ、サイズが大きいので、デュビアを与える場合は繁殖させて小さいデュビアを与えられるようにするか、小さなデュビアを消費できる数だけ購入する様にしましょう。
繁殖も簡単なので、飼育している爬虫類が多い場合はデュビアの繁殖に挑戦してみるのもいいと思います。
レッドローチ
レッドローチもゴキブリです。レッドローチは見た目は完全にゴキブリなので、ゴキブリが苦手な人は飼育するのは難しいと思います。
デュビアに比べてサイズが小さいのでカナヘビの飼育には使いやすい餌です。匂いはデュビアより臭いですが、コオロギよりは臭くありません。レッドローチは水切れや餌切れに強く、飼育も簡単なので餌としては使いやすいです。
レッドローチは成長が早いので、飼育しているとすぐに大きくなってしまいます。なので、カナヘビを飼育するだけにレッドローチを飼育するのは大変だと思います。
レッドローチは体が丈夫で、ストックしている時のロスも少ないので、見た目さえ気にしなければとても使いやすい餌です。
人工フード
もしピンセットから餌を食べるのであれば人工フードを与えて飼育することができます。人工フードであれば簡単に用意することができるので、カナヘビを飼育するときには使いやすいと思います。
レオパゲルやグラブパイなどの昆虫食の爬虫類用の人工餌が販売されています。そういったものであれば昆虫を飼育する必要もなく、常温や冷蔵庫で保存しておくことができて、簡単に使用することができるので飼育にオススメです。
カナヘビの赤ちゃんにオススメの餌
カナヘビが小さい場合は当たり前ですが餌も小さくないと食べることができません。大きくてもカナヘビの頭と同等ほどのサイズの餌しか食べることができません。カナヘビの赤ちゃんを飼育する場合はサイズのあった餌を用意する必要があります。
先ほどいくつかカナヘビを飼育する際にオススメの餌を紹介しましたが、カナヘビの赤ちゃんを飼育する場合に特におすすめなので、「ヨーロッパイエコオロギ」と「レッドローチ 」です。
ヨーロッパイエコオロギは販売しているお店も多く、SSサイズからLサイズまで様々な大きが販売されています。SSサイズは5ミリほどのとても小さいサイズなので、カナヘビの赤ちゃんにも与えることができます。
レッドローチはヨーロッパイエコオロギよりも少し大きくて、5mmほどから1cmのサイズのものが販売されています。
どちらも時間が食べば成長して大きくなるので、大きくなるまで食べきれる量を購入するようにしましょう。
カナヘビの給餌方法について
カナヘビに餌を与えるのはそんなに難しくありません。
カナヘビは食欲が旺盛なので、飼育を始めた日からすぐに餌を食べてくれることが多いです。餌を与える際はピンセットから餌を与える方法と、ケージ内に生き餌を放す方法と、餌皿から餌を与える方法があります。
それぞれの餌の与え方について紹介します。
ケージ内に生き餌を放す
飼育ケージに直接生きた昆虫を入れておけば食べてくれます。生き餌の動きが早くうまく食べられないことがあるので、生き餌をケージ内に放す際は、生き餌の後ろ足を切って動きを遅くしてから与えるのがオススメです。
また、入れすぎてしまうとカナヘビが生き餌に噛まれてしまい、餌を怖がる様になることがあるので、入れすぎに注意してください。
ピンセットから餌を与える
ピンセットで昆虫をつまんで、顔の前まで持っていけば餌を食べてくれます。
カナヘビは食欲が旺盛なので、生き餌をピンセットでつまんで顔の前に持っていくとすぐに食べてくれることが多いです。
飼育環境に慣れていないと怖がってピンセットから餌を食べてくれないこともあるので、飼育を始めたばかりだとピンセットから食べてくれないことがあります。もし食べない場合はケージ内に生き餌を放して、またチャレンジしてみてください。
何度か繰り返せばピンセットからの給餌に慣れてくれます。ピンセットからの給餌に慣れてくれれば、人工餌で飼育することができるので、ピンセットからの給餌に慣れさせるのがオススメです。
餌皿から餌を与える
餌皿に生き餌を入れてケージ内に設置しておく方法が1番簡単な餌の与え方です。
コオロギやレッドローチなどは餌皿から出てしまうので、餌皿から餌を与えう場合はサシやミルワームなどの脱走されない餌を与えるようにしましょう。
ただ、餌皿にサシなどの生き餌を入れてケージ内に設置しておくだけでいいので管理が楽でオススメです。
餌を与える頻度
カナヘビが小さい場合は毎日食べるだけ餌を与えるようにしましょう。毎日餌が食べられるように毎朝餌が減って入れば新しく飼育ケースに餌を入れてください。
大人のカナヘビは毎日餌を食べなくても大丈夫です。大人のカナヘビを飼育する場合は3日に1回ほど餌を与えるようにしましょう。
サプリメントについて
最初にも少し紹介しましたが、カナヘビを飼育する際は3回に1回ほど昆虫にカルシウム剤をまぶしてから与えるようにしましょう。
カルシウムが不足すると骨をちゃんと形成することができず、骨が脆くなってしまうくる病という病気になってしまいます。
カルシウムが不足するとすぐになる訳ではありませんが、長期的にカルシウムが不足するとくる病になってしまうので気をつけてください。カルシウムだけでなく、ビタミンが不足することでもクル病になってしまいます。
昼行性のトカゲで日光浴をすることで体内にビタミンを作り出します。日光浴ができないとクル病になってしまうので、バスキングライトと紫外線ライトを設置してちゃんと日光浴ができる様にしておきましょう。
カナヘビが餌を食べない時の対処法
カナヘビを飼育していると餌を食べなくなってしまうことがあります。餌を食べなくなってしまう原因は飼育環境や体調など様々ななのでそれぞれの原因について紹介します。
ストレスが溜まっている
飼育環境に慣れていなかったり、他のカナヘビと一緒に飼育をしていることが原因でストレスが溜まっていると餌を食べてくれなくなることがあります。
落ち着ける環境でないと餌を食べてくれないことがあるので、飼育を初めたばかりで、飼育環境に慣れていないと餌を食べないことがあります。
人に触られたり、飼育ケージの中をいつも覗かれているとストレスになってしまうので、飼育を始めたばかりは特に構ったりせずにそっとしておきましょう。
室温が低い
気温が下がってくると代謝が下がり餌も食べなくなります。
カナヘビなどの昼行性の爬虫類は日光浴をして体温をあげてから餌を探すなどの活動を始めます。ちゃんと日光浴をして体温が上がらないと餌を食べてくれないので、カナヘビを飼育する場合はバスキングライトを用意して日光浴ができるようにしてください。
ホットスポットは40度前後になるようにして、ケージ内の温度は20〜25度前後で温度勾配ができるように保温器具を設置するようにしましょう。
餌が好きじゃない
単純に餌が好きじゃなくて食べないこともあります。
同じ餌を与えていると急に飽きて食べなくなってしまったり、生き餌に噛まれたことが原因で餌を怖がってしまって食べないことがあります。
違う餌を与えてみると簡単に食べてくれることもあるので、餌を食べない場合は違う生き餌を与えてみるのもおすすめです。
病気や怪我をしている
1番怖いのが病気や怪我が原因で餌を食べないことです。
コオロギやミルワームの牙など硬い部分で怪我をしてしまった場合やクル病や膿瘍などの病気が原因で餌を食べなくなってしまうことがあります。
怪我であれば自然に治癒しますが、病気になってしまったら動物病院でみてもらう必要があります。カナヘビに餌を与える際は日頃から病気や怪我にならないように気をつけてください。
コオロギを与える場合は硬い後ろ足切って、ミルワームを与える際は硬い牙の部分を切ってから与えると安全です。また、クル病はビタミンDとカルシウムが不足することでなる病気です。
日光浴をして紫外線を浴びることで体内でビタミンDを作り出すので、バスキングライトの他に紫外線ライトも忘れないで設置してください。また、カルシウムが不足しないように生き餌を与える際はカルシウム剤を添加してから餌を与えるようにしましょう。
トカゲを飼うときの注意点とペットにオススメのトカゲはこちらの記事で、トカゲを飼おう!!トカゲ飼育するときの注意点とオススメのトカゲを紹介!!こちらの記事も読んでみてください。
爬虫類の飼育に必要な設備についてはこちらの記事で紹介しているので、爬虫類の飼育を考えている方は読んでみてください。














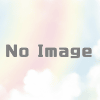









ディスカッション
コメント一覧
ありがとう!!