ヤモリの餌について!オススメの餌や餌の頻度や与え方・保存方法について紹介!!
ヤモリは春先や夏場に見かけることの多い爬虫類です。家の窓に張り付いていたりすることも多いでの飼ってみたい人も多いと思います。ヤモリを捕まえたけどどうやって飼育すればいいのかわからない、そもそもヤモリってなにを食べるのか知らないって人もいるんじゃないでしょうか。今回の記事では、ヤモリを飼育するときにオススメの餌を紹介します。
ヤモリを飼育してみたいけど、どんな餌を食べるのかわからないって人も多いですよね。飼育してみたくてもどんな餌を食べるのかわからないと飼育することはできません。
結論から言えばヤモリは肉食の爬虫類なのでコオロギなどの昆虫を食べます。
コオロギの他にもデュビアやレッドローチなどが爬虫類用の餌として販売されているので、餌用の昆虫を与えることで飼育することができます。ただ、昆虫を与えているだけでは、くる病という病気になってしまいます。
くる病を予防するにはカルシウムが不足しないようにカルシウムパウダーをまぶしてから餌を与える必要があります。
ヤモリを飼ったことがないと、どうやって餌を与えればいいかなど、よくわからないことも多いと思います。今回の記事では、ヤモリを飼育するときにオススメの餌や餌の与え方について紹介するので、ヤモリを飼ってみたいと思う人はぜひ読んでみてください。
それでは、ヤモリを飼育するときにオススメの餌を紹介します。
ヤモリってなにを食べるの?
ヤモリは肉食の爬虫類で、昆虫を食べます。
夏場など、自宅の壁や神社の壁でヤモリを見つけたことがある人は多いと思います。
なんで壁に張り付いているのかって疑問に思う人も多いと思いますが、ヤモリは餌を取るために壁に張り付いています。ヤモリは家の壁や神社の壁に張り付いて、神社や自宅の光に集まる蛾などの昆虫を捕食しています。
ヤモリは昆虫を食べるので、ヤモリを飼育する場合は昆虫を用意する必要があります。
餌用の昆虫は爬虫類や熱帯魚の餌としてペットショップなどで販売しています。ペットショップで購入できるので、餌の入手はそれほど大変ではありません。中でもコオロギとミルワームは販売しているお店も多いので、何軒かペットショップを回れば購入することができると思います。
コオロギでもミルワームでも飼育することができますが、コオロギのほうが栄養に偏りがないので、ミルワームよりもコオロギのほうがオススメです。ミルワームはコオロギに比べて脂肪分が多いので、与え過ぎてしまうと脂肪過多になってしまうことがあるので与えすぎに注意してください。
リンとカルシウムの比率について
爬虫類を飼育する場合はりんとカルシウムの比率に気をつけてください。爬虫類を飼育する場合はリンとカルシウムの比率は1:1〜2:1が理想と言われています。
リンの摂取量が多いとカルシウムを吸収することができずに排泄されてしまいます。人工餌であればリンとカルシウムの比率が2:1に近い比率なので問題ありませんが、生き餌はリンとカルシウムの比率が2:1にはほど遠いので、生き餌を与える際はカルシウム剤を添加してから与える必要があります。
カルシウムの必要性については後半のくる病についてで詳しく紹介します。
ペットに人気のヤモリについて
ヤモリと言えばニホンヤモリが有名ですが、様々な種類のヤモリがペットとして販売されています。
主食が昆虫なのは変わりませんが、種類によっては飼育方法も異なるので、ヤモリを飼育する場合は種類に合った方法で飼育する様にしましょう。
それではペットに人気のヤモリの種類について紹介します。
ヒョウモントカゲモドキ
ヒョウモントカゲモドキはレオパの相性でも知られているヤモリです。
飼育が簡単なのでペットとしての人気が高く、ペットショップでも良く販売されているヤモリです。餌は他のヤモリと同様に昆虫が主食です。
ヤモリの仲間ですが、ニホンヤモリの様に壁を登ることができないので脱走される心配が少なく、水槽で飼育することができます。
販売価格も安く、安いものでは5,000円ほどから販売されています。販売価格はモルフによって違います。モルフとは品種改良によって生まれた種類のことを言い、ヒョウモントカゲモドキは品種改良が盛んに行われていて、様々な模様や体色のモルフがいます。
最近できたモルフほど販売価格は高くなり、全身が黒い「ブラックナイト」は20万円ほどで販売されています。
クレステッド・ゲッコー
クレステッドゲッコーは和名ではオウカンミカドヤモリと言います。
名前の通り頭部に突起がありこれが王冠の様に見えることからこの名前がつけられました。日本では英名のクレステッドゲッコーからとった、クレスの相性で呼ばれることが多いです。
ニホンヤモリと同様に樹上性のヤモリなので、飼育する場合は高さのあるケージと登り木が必要になります。小さいケージで飼育すると同じ場所に居ることが多くなり、尻尾が曲がってしまうことがあります。
販売価格はショップによって異なりますが1〜3万円ほどで販売されていることが多いです。
ニホンヤモリ
ニホンヤモリは北海道を除く日本全国に生息しているヤモリです。日本に広く生息しているヤモリで民家に住み着くことも多いので昔から親しまれているヤモリです。
飼育は簡単なヤモリですが、臆病な性格をしているので、飼育する際はストレスを与えない様に注意してください。必要以上に触ったり、ずっと観察していると怖がって餌を食べなくなってしまうことがあるので、飼育環境に慣れるまではそっとしておきましょう。
ペットショップで販売されることもありますが、個人でも捕まえることができるので、ショップではあまり取り扱われないことが多いです。
トッケイヤモリ
トッケイヤモリは中国や東南アジアに広く生息しているヤモリです。トッケイ、トッケイ、と鳴くことからこの名前が付いています。
飼育は簡単で体も丈夫なヤモリですが、35cmほどまで成長するので飼育する場合は大きな飼育ケージが必要になります。鳴き声が大きいので飼育する場合はその点に注意してください。
ヒルヤモリ
ヒルヤモリはヤモリの中では珍しく昼行性のヤモリです。
ヒルヤモリにもいくつか種類がありますが、ペットとしてよく飼育されるのは「ヨツメヒルヤモリ」です。綺麗な緑色をしているヤモリで前足の付け根に黒い模様があり目が4つある様に見えることから名付けられました。
体長は最大で15cmほどまで成長するので、飼育する場合は高さが30cm以上のものを選ぶ様にしてください。
綺麗なヤモリですが販売価格が意外に安く1万円前後で販売されることが多いです。ヒルヤモリは昼行性のヤモリなので飼育する場合は紫外線ライトが必要になります。
ガーゴイルゲッコー
ガーゴイルゲッコーは大理石の様な模様をしていて、東部にツノ状の突起があるヤモリです。ツノ状の突起と大理石の様な模様からガーゴイルを模った石像に似ているのでこの名前が付いています。
怖い名前をしていますが性格はおとなしく動きもゆっくりなのでハンドリングすることができます。販売価格は他のヤモリに比べて高く2万円ほどで販売されていることが多いです。
ヤモリの飼育にオススメの餌
それでは具体的にヤモリの飼育にオススメの餌を紹介します。ヤモリを飼育する場合は、ヤモリの体長に合わせて餌を選ぶようにしましょう。
あまり大きな餌を与えてしまうと、一度食べた餌を吐き出してしまったりすることがあるので注意してください。
| ヤモリにオススメの餌 | 特徴 |
| コオロギ | 入手がしやすい。ヤモリの飼育で一般的な餌 |
| ミルワーム | 入手がしやすい。保存が楽、栄養価があまり良くない。 |
| デュビア | 飼育がしやすい。匂いが少ない。サイズが大きい |
| レッドローチ | 飼育がしやすい。サイズが小さい。飼育が簡単 |
| 人工餌 | ピンセットから給餌する必要がある。 |
私はヤモリに生き餌を与える際はレッドローチを与えることが多いです。コオロギの様に鳴くことがなく、共食いもほとんど起きないので飼育がとても楽です。
夏場など室温が高いと動きが早くなるので脱走されない様に注意してください。
コオロギ
コオロギは熱帯魚屋さんやペットショップなどで販売していて、手軽に購入することができるので使いやすい餌の一つです。
コオロギにはヨーロッパイエコオロギとフタホシコオロギの2種類がいます。どちらもそれほど大きな差はないので、近くのペットショップで販売していたり、入手が楽な方を選ぶのがいいと思います。
保存も簡単で夏場暑い季節じゃなければ、そう簡単に死んでしまったりすることはありません。フタホシコオロギは蒸れに弱くケージ内が蒸れると全滅してしまうことがあります。蒸れやすい夏場は風通しがよくて涼しい場所で飼育するようにして、水入れの水が溢れたりしないように注意してください。
コオロギは夏場は成長が早いので、小さいヤモリ用にコオロギを購入しても、コオロギが大きくなって与えられなくなってしまい、コオロギが無駄になってしまうこともあります。
入手がしやすい生き餌ですが、蒸れで全滅してしまったり、共食いが起きやすくてロスも多いです。
コオロギを飼育しよう!爬虫類の餌に最適なコオロギの飼育方法を紹介!!
ミルワーム
ミルワームも熱帯魚やハリネズミなど様々なペットの餌としてよく使われている昆虫です。保存が楽でペットショップでも良く販売されている餌です。ミルワームも冷蔵庫で保存することができます。
皮が厚く消化が遅く脂肪が多いので栄養価はあまり良くありません。おやつ程度に与えるのであればいいかもしれませんが、毎日与えていると脂肪過多になってしまったり、消化不良になったりすることがあります。
ミルワームを与える場合は脱皮したての皮が白くなっているものを与えるのがオススメです。ミルワームの栄養価とミルワームを与えるときの注意点を紹介!!
デュビア
デュビアはコオロギなどと同様に爬虫類やアロワナなどの肉食魚の餌として販売されているゴキブリです。
ゴキブリと聞くと気持ち悪いイメージを持つかもしれませんが、飼育が簡単で水切れにも強く、コオロギのように共食いをしないのでとてもオススメの餌です。
ただ、体長が他の生き餌に比べて大きくなってしまうので、ヤモリの飼育に使用する場合は小さいサイズのデュビアを適量購入するようにしましょう。
デュビアは草食性なので、コオロギよりも匂いが少なく鳴くこともないので、飼育はとても楽です。繁殖させることもできますが、成長がゆっくりなので、繁殖させるのに時間がかかってしまいます。
見た目も日本に生息しているゴキブリとは少し違うのでそれほど気持ち悪くもありません。デュビアは草食性なので、餌はプレコ用の乾燥餌かウサギ用の餌を入れておくようにしましょう。
生野菜も食べることができますが、すぐに痛んでしまいます。生野菜を与える場合は毎日交換するようにしましょう。デュビアの特徴や飼育方法、繁殖方法について紹介!!
レッドローチ
レッドローチもゴキブリです。こちらは見た目は完全にゴキブリです。
見た目がゴキブリですが飼育がとても簡単でコオロギの様に鳴かないので1番オススメの餌です。
デュビアに比べると油のような匂いがして少し臭いですが、飼育も簡単で成長スピードも早いので簡単に繁殖させることができます。
レッドローチはデュビアに比べて動きが早いので、飼育する場合は逃げられないように注意してください。
レッドローチもコオロギと同様の方法で飼育することができます。少し油臭いですが、レッドローチも鳴かないので、コオロギが煩いと思う方はレッドローチがいいと思います。
コオロギに比べて匂いも少なく、鳴き声もなく、飼育も簡単でコオロギのように共食いが起きることもなく、飼育も簡単でロスも少ないので、見た目がきにならない場合はレッドローチを与えて飼育するのがオススメです。レッドローチの飼育方法と繁殖方法について!餌や匂い対策についても紹介!!
人工餌
ヤモリは人工餌で飼育することもできます。ただ、人工餌は飼い主がピンセットで直接与えなければならず、ヤモリのストレスにもなってしまうことがあるので注意が必要です。
野生のヤモリを捕まえて飼育する場合、ヤモリはストレスを感じています。飼い始めたばかりのヤモリは飼育環境に慣れていないので、飼育環境になれるまではコオロギなどの生き餌を飼育ケージの中に入れて、好きに餌が食べられるようにしておくようにしましょう。
飼育環境に慣れてきて飼い主にも慣れてきたら、ピンセットからコオロギなどの餌を与えるようにして、ピンセットからの給餌に慣れさせてから人工餌に切り替える様にしてください。
人工餌はクレステッドゲッコー用のものやレオパ用のものを与えることができます。人工餌は練り餌タイプやペレットタイプなど様々です。ペレットタイプの人工餌なら常温で保存をすることができるので、保存が楽で使いやすいです。
練り餌タイプの人工餌は時間がたてば腐ってしまうので、作ったらものは冷蔵庫で保存して、1週間以内に与えるようにしましょう。
長期間保存したい場合はブロック上に切れ込みを入れてからラップをして冷蔵庫で保管するのがいいと思います。使いたい時に、ブロックを割ってちゃんと解凍させてから与えるようにしてください。
ブドウ虫
ブドウ虫は釣り餌として使われている蛾の幼虫です。白い芋虫のような見た目をしていて、渓流釣りで使われることが多い幼虫で、春〜秋の渓流釣りのシーズンであれば釣具店で購入することができます。
ブドウ虫は冷蔵庫の野菜室などで保存することができるので、ヤモリの餌としても使いやすいと思います。夏場など暖かい季節は冷蔵庫に入れておかないと1週間ぐらいで悪くなってしまうので気をつけてください。
サイズも少し大きくて3cmほどなので、小さいヤモリを飼育する場合は他の餌を選ぶのがいいと思います。
サシ
サシはカワハギ釣りなどで使われている餌で、紅サシなどと呼ばれています
ハエの幼虫で、サイズが5mmほどと小さいので小型のヤモリを飼育する場合にオススメの餌です。釣り具屋さんで販売しているので、入手がしやすく使いやすい餌です。この餌も冷蔵庫の野菜室であれば1ヶ月ぐらい保存することができるので、管理が楽でオススメです。
常温で保存していると1週間ぐらいで蛹になってしまうので注意してください。
ヤモリの餌の頻度と大きさについて
餌の頻度
ヤモリはそんなにたくさん餌を食べる生き物ではないので、毎日餌を与える必要はありません。
大人のヤモリであれば1週間に2回程度餌をあげるだけで十分です。子供のヤモリを飼育する場合はサイズの小さいコオロギを飼育ケージの中に常に2〜3匹ぐらい入れていつでも餌を食べられる様にしておくのがオススメです。
ただ、サイズが大きかったり数が多かったりするとヤモリが噛まれてしまってコオロギを怖がってしまうことがあるので、入れすぎには注意してください。
餌の大きさについて
餌の大きさは飼育しているヤモリの顔の3分の1ほどの大きさを選ぶようにしましょう。ヤモリは餌を丸呑みするので、あまり餌が大きいと喉に詰まらせてしまうことがあります。
また、大きいと餌を食べてくれないことも多いので、ちゃんと餌が食べられるように適切なサイズの餌を用意しましょう。子供のヤモリを飼育する際は最小のサイズの餌を購入するようにしましょう。
ヤモリの餌の与え方について
ヤモリに餌を与える方法はピンセットで与える方法と飼育ケージに生き餌を放す方法、餌皿を設置する方法があります。それぞれの餌の与え方について紹介します。
ピンセットで餌を与える方法
餌を与える頻度が少ない生き物なので、生きているコオロギをストックしているとすぐに大きくなってしまいます。ピンセットから餌を食べる場合は冷凍のコオロギを解凍して与えたり人工フードを与えることができます。
飼育環境に慣れてくるとピンセットから餌を食べるようになるので、落ち着いているようだったらピンセットを使って餌をあげてみてください。ピンセットで餌を与えるときは、コオロギなどの餌をピンセットでつまんで、この前で小刻みに揺らすと反応して食べてくれます。
ピンセットから給餌することで、餌をどのぐらい食べているか確認することができます。健康状態を確認するためにも大切なので、ピンセットからの給餌に慣れさせておくのがオススメです。
飼育ケージに生き餌を放す方法
飼育を始めたばかりだと警戒心が強くピンセットから餌を食べてくれません。飼い始めは生き餌をケージ内に放して給餌してください。
コオロギやレッドローチなどの生き餌にカルシウム剤をまぶして飼育ケージに餌を放すことで、ヤモリが勝手に餌を食べてくれます。
この方法で餌を食べない場合は、水分不足か餌のサイズが大きい可能性があります。水入れからは水を飲まないことがあるので、ヤモリを飼育する際は霧吹きをして、ケージ内に水滴をつけておきましょう。
餌皿を設置する方法
ケージ内に餌皿を設置してそこにミルワームやサシなどの幼虫を入れておくことでヤモリに餌を与えることができます。
爬虫類用に販売されている餌皿は返しがついていて、ミルワームなどの幼虫が逃げないようになっています。餌皿からの給餌であればどのぐらい餌を食べたのかを確認することができ、管理もしやすいです。
ヤモリに餌を与えるときの注意点
コオロギを飼育ケージに入れているとコオロギがヤモリを噛んでしまうことがあります。コオロギやミルワームに噛まれると怖がって餌を食べなくなってしまうことがあります。
飼育ケージの中に生き餌を入れすぎると噛まれることがあるので、飼育ケージに餌を入れるときは2〜3匹程度にして、食べたのを確認してから次の餌を与えるようにしましょう。
餌のサイズが大きすぎると吐き出してしまったり、餌を食べないことがあります。与える餌はヤモリの頭の3分の1ぐらいの大きさのものを与えるようにしましょう。
ヤモリの赤ちゃんの餌は何がいい?ヤモリのベビーを飼育するときの餌について紹介!
ヤモリが餌を食べないときの対処法
ヤモリなどの爬虫類を飼育していると急に餌を食べなくなってしまうことがあります。
餌をたくさん食べる生き物ではないので、単純にお腹がいっぱいで食べないこともありますが飼育している方からすると心配ですよね。
温度が低い
もしヤモリが餌を食べない場合は飼育ケージ内の温度を確認してみてください。ヤモリは変温動物なので気温が低くなると代謝が下がって餌を食べる量が少なくなります。
餌を変えていないのに急に食べなくなった場合は室温が低くなっていて、冬眠の準備に入っている可能性があります。10度を下回ってくるとヤモリは冬眠の準備に入ってしまうので、室温は20度前後で安定するようにしておきましょう。
水分不足
喉が渇いていると餌を食べないことがあります。
ヤモリは水入れから水を飲まないことがあるので、ヤモリを飼育する場合は霧吹きをしてケージ内に水滴をつけておくようにしましょう。動く水は飲んでくれるので、水滴をつけておくことで舐めて水を飲んでくれます。
床材の誤食をしたり、水分がちゃんと取れていないと腸閉塞になってしまうことがあります。腸閉塞になるとフンをすることができないので、餌を食べなくなります。
妊娠している
妊娠しているヤモリは餌を食べないので、ヤモリが餌を食べないときは妊娠している可能性もあります。お腹を見て、卵が左右に1つずつあれば妊娠しているので、餌を食べなくてもそこまで心配しなくて大丈夫です。
ヤモリの餌やりについて!ヤモリの餌の与え方や餌付けについて紹介!!
くる病について
しっかりとカルシウムを摂取することができないとくる病という病気になってしまいます。
これはヤモリに限らず人間にもなりえる病気です。カルシウムが不足していたり、カルシウムの吸収に必要なビタミンDが不足することで起こる病気です。
くる病になると骨をうまく形成することができないので、脚や背骨が曲がってしまったり、簡単に骨が折れてしまったりします。
カルシウムが不足しないようにすることで予防することができますが、重症化すると命に関わる病気なのでヤモリを飼育する際は注意してください。
くる病を予防するには3匹に1回ほど餌にカルシウムパウダーをまぶしてから餌を与えるだけで大丈夫です。
人工餌の場合は必要な栄養素が含まれていて、カルシウムもしっかり入っているので、問題ありませんが、生き餌で飼育する場合はカルシウムが不足してしまうので、3匹に1回はカルシウムパウダーをまぶすようにしてください。
生きている昆虫にカルシウム剤をまぶしてからケースに入れていると、ヤモリが食べる前にカルシウム剤が取れてしまっている可能性があります。なので、ヤモリに餌を与える際は食べきれる量だけにしてケージ内に餌が残らないように調整してください。
ヤモリの飼育方法はこちらの記事でも詳しく紹介しているので、こちらも読んでみてください。
爬虫類の飼育に必要な設備についてはこちらの記事で紹介しているので、爬虫類の飼育を考えている方は読んでみてください。


























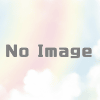







ディスカッション
コメント一覧
初めまして、生き餌以外のトカゲの餌とか
ありますでしょうか?
(ロボロフスキーヤモリを飼うつもりなんですけど…)
コメントありがとうございます。
生き餌以外の餌についてですが、レパシースーパーフードグラパイなどの人工餌を与えるか、冷凍コオロギを与えるかになると思います。
個体差があるので絶対に食べるとは言い切れませんが、グラパイや冷凍コオロギであれば問題なく食べると思います。
こんばんは!子ヤモリを捕まえました、可愛くて飼いたいのですが、コオロギは気持ち悪いので買いたくないんですが、ミルワームなら子ヤモリでも食べてくれるでしょうか?
セットはだいたい揃ってます。
コメントありがとうございます。
ミルワームも食べます。ただ、野生のヤモリは捕まえたばかりだとエサを食べないことがあるので、ミルワームを食べない場合はコオロギも用意した方がいいと思います。
こんにちは。
早速ですが、バッタなどは食べるのでしょうか
コメントありがとうございます。
バッタやクモなどの昆虫も食べます。
サイズが合っている昆虫であれば大体食べるので、近所で昆虫を捕まえられるなら、捕まえた昆虫を与えるのもいいと思います。
デュビアは、赤ちゃんも食べるんですか?
コメントありがとうこざいます。
ヤモリの赤ちゃんには少し大きいと思います。
レッドローチの方がサイズが小さいので、レッドローチがオススメです。